「茶道具・湯呑・急須 > その他」の商品をご紹介します。

餌ふご浄益形・浄益型【茶器/茶道具 建水】 唐銅(唐金) エフゴ型(餌畚型) 中 約535g 定番品 kensui kennsui こぼし 水こぼし
重量約535~585g サイズ約直径14.2×高9.2cm 約口径12.4cm 素材唐銅製 箱紙箱 R4/丸の山N19-2宮(R5/丸吉N31大・18700) 【コンビニ受取対応商品】建水 建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。(蓋置も同じ) 建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。 材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。 袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。 その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。 七種の建水 大脇差、差替、棒の先、鉄盥、鎗の鞘、瓢箪、餌ふご 脇差…利休愛用の形といい、黄瀬戸で好まれた、腰につける脇差に連想して名付けられたようです。 胴が捻貫のようになっている円筒形で、やや背の高いもの 棒の先・槍の鞘…細長い形の物で、蓋置は吹貫や駅鈴を柄杓の柄に通して使います。 鉄盥…平建水で、浅くて背の低い。 桑小卓に使われます。
14960 円 (税込 / 送料別)

唐銅製七種蓋置です。【茶道具】【送料無料】唐銅七種蓋置蟹(かに)(ボール箱)
利休が選んだとされる7種類の形の蓋置。東山御物にあり、足利義政が慈照寺の庭に十三個の唐金の蟹を景として配し、その一つを紹鴎が蓋置に用いたのがその始まりと伝えられます。 素材:唐銅製唐銅とは、銅に亜鉛や真鍮を加えた合金で茶道具はじめ美術品にも多く使われる金属です。七種蓋置(しちしゅふたおき)とは、千利休が選んだと称されている、「火舎香炉」、「五徳」、「三葉」、「一閑人」、「栄螺」、「三人形」、「蟹」の七種類の蓋置です。 七種蓋置には、それぞれ特別な扱いがあります。 火舎蓋置(ほやごうろふたおき)とは、火舎のついた小さな香炉を蓋置に見立てたものです。 火舎は、火屋・穂屋とも書き、香炉・手焙・火入などの上におおう蓋のことで、蓋のついた香炉のことを火舎香炉と呼びます。 七種蓋置のうち、最も格の高いものとして扱われ、主に長板や台子で総飾りをするときに用います。 一閑人蓋置(いっかんじん ふたおき)とは、井筒形の側に井戸を覗き込むような姿の人形がついた蓋置です。 一看人、一漢人とも書き、井看人(せいかんじん)、井戸覗(いどのぞき)とも、惻隠蓋置(そくいんのふたおき)ともいいます。 五徳蓋置(ごとく ふたおき)とは、輪に三本の柱が立ち、その先端が内側に曲がり爪状になっている蓋置です。 炉や風炉中に据えて釜を載せる五徳をかたどった蓋置です。 火卓とも書き、隠家、隠架、陰架(いんか、かくれが)ともいいます。 五徳蓋置は、火舎蓋置に次ぐ格の蓋置として、台子、袋棚にも用いられますが、透木釜、釣釜を使う炉の場合や、切合の風炉の場合など、五徳を使用しない場合に用います。 栄螺蓋置(さざえ ふたおき)とは、栄螺の形をした蓋置です。 栄螺貝の内部に金箔を押したものを使ったのが最初といわれ、のちにこれに似せて唐銅や陶磁器でつくたものを用いるようになったといわれます。 置きつけるときは口を上に向けて用い、飾るときは口を下に向けて飾ります。 三葉蓋置(みつば ふたおき)とは、大小の三つ葉を上下に組み合わせた形の蓋置です。 ふつうは大きな三つ葉形と小さな三つ葉形が背でくっついた形で交互についています。 使うときは、大きな葉を上にして、棚に飾る特は大きな葉を下にします。 三人形蓋置(みつにんぎょう ふたおき)とは、三人の唐子が外向きに手をつなぎ輪になった形の蓋置です。 三閑人・三漢人・三唐子ともいいます。 中国では筆架・墨台で文房具の一つで、それを蓋置に見立てたものです。 三体の内の一体だけ姿の異なる人形があり、その人形を正面とします。 蟹蓋置(かに ふたおき)とは、蟹の形をかたどった蓋置です。 文鎮や筆架などの文房具を蓋置に見立てたものといわれます。 蟹の頭のほうを正面とします。 東山御物にあり、足利義政が慈照寺の庭に十三個の唐金の蟹を景として配し、その一つを紹鴎が蓋置に用いたのがその始まりと伝えられます。
8500 円 (税込 / 送料込)
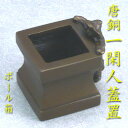
唐銅製七種蓋置です。【茶道具】【送料無料】唐銅七種蓋置一閑人(ボール箱)
利休が選んだとされる7種類の形の蓋置。一閑人蓋置(いっかんじん ふたおき)とは、井筒形の側に井戸を覗き込むような姿の人形がついた蓋置です。 一看人、一漢人とも書き、井看人(せいかんじん)、井戸覗(いどのぞき)とも、惻隠蓋置(そくいんのふたおき)ともいいます。 。素材:唐銅製唐銅とは、銅に亜鉛や真鍮を加えた合金で茶道具はじめ美術品にも多く使われる金属です。七種蓋置(しちしゅふたおき)とは、千利休が選んだと称されている、「火舎香炉」、「五徳」、「三葉」、「一閑人」、「栄螺」、「三人形」、「蟹」の七種類の蓋置です。 七種蓋置には、それぞれ特別な扱いがあります。 火舎蓋置(ほやごうろふたおき)とは、火舎のついた小さな香炉を蓋置に見立てたものです。 火舎は、火屋・穂屋とも書き、香炉・手焙・火入などの上におおう蓋のことで、蓋のついた香炉のことを火舎香炉と呼びます。 七種蓋置のうち、最も格の高いものとして扱われ、主に長板や台子で総飾りをするときに用います。 一閑人蓋置(いっかんじん ふたおき)とは、井筒形の側に井戸を覗き込むような姿の人形がついた蓋置です。 一看人、一漢人とも書き、井看人(せいかんじん)、井戸覗(いどのぞき)とも、惻隠蓋置(そくいんのふたおき)ともいいます。 五徳蓋置(ごとく ふたおき)とは、輪に三本の柱が立ち、その先端が内側に曲がり爪状になっている蓋置です。 炉や風炉中に据えて釜を載せる五徳をかたどった蓋置です。 火卓とも書き、隠家、隠架、陰架(いんか、かくれが)ともいいます。 五徳蓋置は、火舎蓋置に次ぐ格の蓋置として、台子、袋棚にも用いられますが、透木釜、釣釜を使う炉の場合や、切合の風炉の場合など、五徳を使用しない場合に用います。 栄螺蓋置(さざえ ふたおき)とは、栄螺の形をした蓋置です。 栄螺貝の内部に金箔を押したものを使ったのが最初といわれ、のちにこれに似せて唐銅や陶磁器でつくたものを用いるようになったといわれます。 置きつけるときは口を上に向けて用い、飾るときは口を下に向けて飾ります。 三葉蓋置(みつば ふたおき)とは、大小の三つ葉を上下に組み合わせた形の蓋置です。 ふつうは大きな三つ葉形と小さな三つ葉形が背でくっついた形で交互についています。 使うときは、大きな葉を上にして、棚に飾る特は大きな葉を下にします。 三人形蓋置(みつにんぎょう ふたおき)とは、三人の唐子が外向きに手をつなぎ輪になった形の蓋置です。 三閑人・三漢人・三唐子ともいいます。 中国では筆架・墨台で文房具の一つで、それを蓋置に見立てたものです。 三体の内の一体だけ姿の異なる人形があり、その人形を正面とします。 蟹蓋置(かに ふたおき)とは、蟹の形をかたどった蓋置です。 文鎮や筆架などの文房具を蓋置に見立てたものといわれます。 蟹の頭のほうを正面とします。 東山御物にあり、足利義政が慈照寺の庭に十三個の唐金の蟹を景として配し、その一つを紹鴎が蓋置に用いたのがその始まりと伝えられます。
8500 円 (税込 / 送料込)

高級茶道具掘出し物市、開催中! 大特価品、見切り品、多数あり! ユーズド商品ならではの大特価!(二月☆特売品)兵庫県 出石焼 炉舟作 桶川水指 堀内宗完(兼中斎)宗匠箱・花押替塗蓋添 【中古・美品】
←写真をクリックすると拡大表示されます。 ★ユーズド商品です。 水指は無疵でとてもきれいな状態です、拡大画像にてご確認ください。 茶会に使えるお品です。 ※雪輪棚にお使いになられていたようですが、背の低い水指で袋棚にも使えます。 ※作者である炉舟についてはわかりませんでした。 ※寸法 高12.5cm 径17.8cm 蓋径12cm 共箱 ★この商品は特売品担当、増田がサポートしています。●堀内宗完 表千家流堀内家十二代。兄幽峰斎が33才で急逝のため、表千家即中斎のもとで修行の後十二代を襲名する。
60000 円 (税込 / 送料別)

送料無料淡海焼き・ぜぜ焼き【茶器/茶道具 建水】 膳所焼き 棒の先 岩崎新定作(陽炎園) (遠州七窯の一) kensui kennsui こぼし 水こぼし
サイズ約天直径12.2×高12cm 約底直径8.2cm 作者岩崎新定作[陽炎園(遠州七窯の一)] 箱木箱 (野吉大・り)(・38900) 【コンビニ受取対応商品】建水 建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。(蓋置も同じ) 建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。 材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。 袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。 その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。 七種の建水 大脇差、差替、棒の先、鉄盥、鎗の鞘、瓢箪、餌ふご 脇差…利休愛用の形といい、黄瀬戸で好まれた、腰につける脇差に連想して名付けられたようです。 胴が捻貫のようになっている円筒形で、やや背の高いもの 棒の先・槍の鞘…細長い形の物で、蓋置は吹貫や駅鈴を柄杓の柄に通して使います。 鉄盥…平建水で、浅くて背の低い。 桑小卓に使われます。 【初代 岩崎健三】膳所の人 明治生まれ 1919年大正08年 山元春挙画伯とはかり再興 【2代 岩崎新定】初代健三の長男 1913年大正02 年生まれ 京都高等工芸学校陶磁器科卒 1987年昭和62年 膳所焼美術館を設定 1985年昭和60年 滋賀県伝統的工芸品指定 1991年平成03年 通産省より伝統産業功労者表彰 2010年平成22年 現在尼膳所焼で製陶中 現在、染付・赤絵等いろいろな物が製作される。代表作 茶入「大江山」 ----------------------------------------- 【陽炎園】 現在遠州七窯の一つに数えられる。 日本画家 山元春挙画伯が「東海道名所絵図」にも描かれた名勝「陽炎の池」が庭内にあることから命名された。 当時、小堀遠州は近江奉行であったことなどから、遠州の指導が考えられる。 遠州好みの茶入として「大江山」「白雲」が有名。
30690 円 (税込 / 送料別)

送料無料【茶器/茶道具 建水】 唐銅(唐金) 棒の先 般若勘溪作 kensui kennsui こぼし 水こぼし
重量約355g サイズ約直径14.6×高8.1cm 素材唐銅 作者般若勘溪作 箱木箱 (野目大)(44920) 【コンビニ受取対応商品】建水 建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。(蓋置も同じ) 建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。 材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。 袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。 その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。 七種の建水 大脇差、差替、棒の先、鉄盥、鎗の鞘、瓢箪、餌ふご 脇差…利休愛用の形といい、黄瀬戸で好まれた、腰につける脇差に連想して名付けられたようです。 胴が捻貫のようになっている円筒形で、やや背の高いもの 棒の先・槍の鞘…細長い形の物で、蓋置は吹貫や駅鈴を柄杓の柄に通して使います。 鉄盥…平建水で、浅くて背の低い。 桑小卓に使われます。 【般若勘溪(本名 昭三)】鋳物師 1933年昭和08年 癸酉生まれ 1949年昭和24年 父のよ吉の稼業を手伝う~以来研鑽する 1969年昭和44年 日本伝統工芸展初入選(以後、35回) 1972年昭和47年 日本工芸会正会員に認定される 1978年昭和53年 総本山善通寺済世橋の真言八宗文字入り、大擬宝珠製作 1986年昭和61年 人間国宝 香取正彦氏の梵鐘研修会受講 宮内庁より正倉院御物の復元を依頼され砂張物や黄銅合子を制作 2003年平成15年 高岡市伝統工芸産業技術保持者に指定される
36960 円 (税込 / 送料別)

送料無料三人官女桃の節句・ひなまり・雛祭り・桃の花唐金【茶器/茶道具 菓子器 ひな祭り】 干菓子器 唐銅 桃桜菱紋(三花彫) 三人形 金谷宗林作
サイズ約外直径22.4×全高5.2cm 約内径19. 約台高4.5cm 素材唐銅 作者2代 金谷宗林作 箱木箱 3個限定/輪山(有輪丸-1引宮・61150) 【コンビニ受取対応商品】雛飾りの橘と桜の置き方 雛壇に向かって、左側が「橘」・ 右側が「桜」 です 「左近の桜、右近の橘」で3月3日は、左近の桜(さんがつみっかは、さこんのさくら)と覚えます。 右に、左近の桜 左に、右近の橘なぜ逆になるのでしょう。 そのひみつは、天皇の高御座(たかみくら)と京都御所の紫宸殿(ししんでん)にあります。 平安宮の南殿(紫宸殿 ししんでん)では中央に天皇の御座・高御座(たかみくら)があり、その東側には皇后の御座・御帳台(みちょうだい)があります。 そして、前庭には、桜と橘が植えられていますね。 私たちが外から見ると紫宸殿に向かって、左が「右近の橘」・右が「左近の桜」です。 これを、天皇側から、内裏にて北を背に南面の庭を御覧になったとすると、日が昇る方が「東」=左上位=【桜】・日が沈む方が「西」=右下位=【橘】です。 ですから【左近の桜・右近の橘】が、正しいのです。 【金谷宗林】 1935年昭和10年 高岡生まれ 1958年昭和33年 京都鋳物を研修 1963年昭和38年 高岡にて茶道具製作に専心 1975年昭和50年 高岡商工展入選 1979年昭和54年 高岡市伝統工芸士なる 奥州、山形の鋳物の伝統を受け継ぎ、鉄と炎の自然美を追求し製作に邁進、茶の湯道具に研鑽中 【2代 金谷宗林】 1969年昭和44年生 富山県高岡市在住 工芸技術者
48884 円 (税込 / 送料別)

送料無料淡海焼き・ぜぜ焼き槍の鞘【茶器/茶道具 建水】 膳所焼き 槍鞘 岩崎新定作(陽炎園) (遠州七窯の一) kensui kennsui こぼし 水こぼし
サイズ約直径10.3×高13cm 作者岩崎新定作[陽炎園(遠州七窯の一)] 箱木箱 野山丸岡(野吉大・り)(・38880) 【コンビニ受取対応商品】建水 建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。(蓋置も同じ) 建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。 材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。 袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。 その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。 七種の建水 大脇差、差替、棒の先、鉄盥、鎗の鞘、瓢箪、餌ふご 脇差…利休愛用の形といい、黄瀬戸で好まれた、腰につける脇差に連想して名付けられたようです。 胴が捻貫のようになっている円筒形で、やや背の高いもの 棒の先・槍の鞘…細長い形の物で、蓋置は吹貫や駅鈴を柄杓の柄に通して使います。 鉄盥…平建水で、浅くて背の低い。 桑小卓に使われます。 【初代 岩崎健三】膳所の人 明治生まれ 1919年大正08年 山元春挙画伯とはかり再興 【2代 岩崎新定】初代健三の長男 1913年大正02 年生まれ 京都高等工芸学校陶磁器科卒 1987年昭和62年 膳所焼美術館を設定 1985年昭和60年 滋賀県伝統的工芸品指定 1991年平成03年 通産省より伝統産業功労者表彰 2010年平成22年 現在尼膳所焼で製陶中 現在、染付・赤絵等いろいろな物が製作される。代表作 茶入「大江山」 ----------------------------------------- 【陽炎園】 現在遠州七窯の一つに数えられる。 日本画家 山元春挙画伯が「東海道名所絵図」にも描かれた名勝「陽炎の池」が庭内にあることから命名された。 当時、小堀遠州は近江奉行であったことなどから、遠州の指導が考えられる。 遠州好みの茶入として「大江山」「白雲」が有名。
30470 円 (税込 / 送料別)
